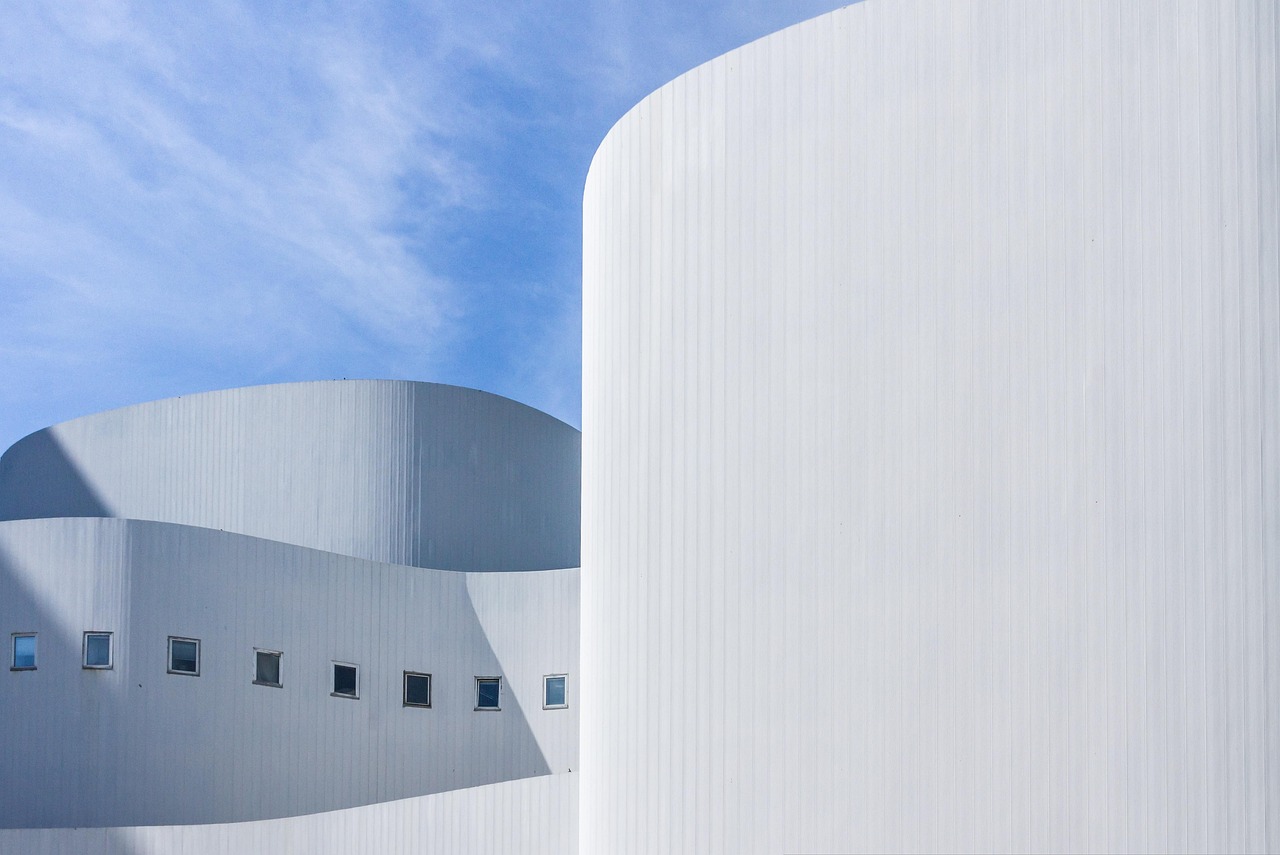こんにちは。仙台の税理士、伊藤です。
最近読んだ本で印象に残ったのが、細谷功さんの『13歳から鍛える具体と抽象』です。
「ものごとを具体と抽象で考える力を身につけよう」という内容で、シンプルながら日常や仕事に直結する示唆が多い一冊でした。
『具体と抽象』とは
具体=身近な事例、抽象=背後にある原則やパターン。
たとえば「カレーを食べる」というのは具体です。
一方で「食事をする」と言えば、カレーに限らずラーメンや寿司も含む広い概念になります。これが抽象です。
この二つを行き来できると、勉強や仕事、人とのコミュニケーションまで幅広く役立ちます。
税務のSNS投稿は具体?抽象?
SNSでは「インボイス登録は必須です!」「法人化すれば節税できます!」といった投稿を目にすることがあります。
しかし、これはあくまで一部の状況に当てはまる具体例に過ぎません。
インボイス登録は取引先の要望や売上規模によって判断が変わりますし、法人化も所得水準や経費、今後の事業計画次第で有利・不利が変わります。
抽象に引き上げて考える
こうした情報を見かけたときは、「これはどんな原則を示しているのだろう?」と抽象化して整理します。
- インボイス制度は「取引先が仕入税額控除を使えるかどうか」に関わる仕組み。
- 法人化による節税は「個人と法人の税率構造の違い」を利用する仕組み。
このように抽象化すると、投稿が伝えようとしている制度の原則が見えてきます。
自分の状況へ具体化する
抽象的な原則をつかんだら、次は自分の状況に当てはめて具体化して考えます。
- 取引先からインボイス登録を求められているか?
- 自分の所得水準では法人化によるメリットが出るのか?
- 節税効果よりも、社会保険や事務負担が増えるデメリットが大きくないか?
こうして「誰かの具体」→「制度の抽象」→「自分の具体」と往復させることで、SNSの断片的な情報に振り回されずに済みます。
税理士の役割は抽象化?
ここで改めて思うのは、税理士の役割自体が「抽象化」ではないかということです。
お客様の質問やSNSで見かけた情報は、多くが「具体的なケース」です。
それを制度の原則やルールに引き上げて整理し、さらにその人の状況に合わせて具体化し直す。
この「抽象化→再具体化」のサイクルをサポートするのが、私たち税理士の仕事だと感じます。
まとめ
『13歳から鍛える具体と抽象』は、知識そのものより「考えるための型」を教えてくれる本です。
税務のSNS投稿を見たときも、この型が役立ちます。
- SNS投稿は「誰かの具体」
- 背後にある「制度の抽象」を押さえる
- それを「自分の具体」に当てはめ直す
そして、それを一緒に整理するのが税理士の役割です。
税務に限らず、日々の情報収集やSNSとの付き合い方にも応用できる考え方だと思います。